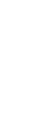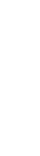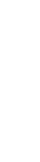CO・OP 生しぼり絹豆腐
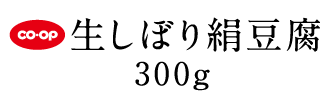

国産大豆100%、凝固剤はにがりのみ、消泡剤不使用。「生しぼり絹豆腐」には、こだわりがいっぱい詰まっています。
雑味がなく、大豆のコクと甘みを味わえる豆腐です。
生しぼりって何?

豆腐を作るには、まず大豆に充分水を吸わせてから、水を加えてすり潰します。その後、煮て豆乳を搾るのが一般的な「煮しぼり」。煮ないで豆乳を搾るのが「生しぼり」です。
豆乳は温度を上げて搾る方がたくさん取れるので、一般的な煮しぼりは、100℃まで上げて作られます。ですが、生しぼりは加熱をしないで豆乳をしぼるので、大豆のコクと甘味を残しつつ、すっきりとした味わいの豆腐となります。 大豆を高温で煮ると皮や芽から雑味が出てくるので、生産者である株式会社マルツネでは、生しぼりにこだわっています。ですが、一般的なのは煮しぼりの豆腐。煮しぼりの“雑味”を“大豆の風味”と感じる人ももちろんいます。どちらがおいしいか、というものではなく、その時作りたい料理や好みに合わせて使い分ければ良いものです。
CO・OP 生しぼりシリーズは、食べるほどに甘みとコクを感じられ、くせがないので毎日食べても飽きず、主役になれるお豆腐です。
北陸産大豆を使用 国産は素材として、おいしい

日本人に合わせ、“おいしい食べ物”になるよう品種改良されてきたのが、国産大豆。張りのある、粒だった見た目からして、輸入大豆とはまるで違います
工場で使用する原料の大豆は、生協以外の製品も含め、100%国産。北陸を中心に複数の産地のJAと契約栽培をすすめており、天候不順となっても安定して原料大豆を確保できるようにしています。農薬や肥料などの使用方法は産地JAが指導し、残留農薬検査なども行っています。
国産大豆の良いところは、食べ物としての品質が高い点。加えて、日本人にとっておいしいものへと品種改良が重ねられてきた点です。日本では、納豆や煮豆など、大豆を丸ごと味わいます。「でも、例えばアメリカでは、大豆と言えば家畜の餌か油の原料であるため、おいしさを追求されているとは言えないのです」とマルツネの近藤恒憲専務。
工場内の井戸水で作っています
豆腐は、約9割が水分。どんな水を使って作るかが、そのおいしさを左右します。
マルツネで使っているのは、工場内にある井戸の水です。工場があるのは、愛知県知立市。在原業平が、湿地に生えるカキツバタの歌を詠んだ地で、工場周辺も、カキツバタの群生地でした。水が豊富な土地なのです。
工場はこの井戸水で清涼飲料水の製造許可を取り、豆乳飲料も作っています。この許可、とても厳しい基準をクリアしなければなりません。それだけ上質の水を使って豆腐を作っているのです。
「洗えるパイプライン」を導入

しぼった豆乳はパイプラインを通って、加熱殺菌や充填ラインに送られます。「このパイプラインは、牛乳工場と同じもの。パイプの中のすみずみまで洗えるようになっているので、豆腐工場用のラインよりも衛生的です。豆腐の日持ちを長くできたのも、このラインを導入できたおかげです」。
カットしません
にがりを混ぜた豆乳を容器に充填するから、「充填豆腐」といいます。フィルムシールで密閉し、熱湯で加熱して固め、冷却するとでき上がりです。
カットの工程がない分、雑菌が入らないので、日持ちのする豆腐になります。昔ながらの水に浸かったものは「カット豆腐」といいます。
豆腐は本来、生しぼりでした
「昔の豆腐はもっとおいしかった」と先輩から聞いた社長が、何が違うのだろうと探求を始め、たどり着いたのが、豆腐はもともと生しぼりであり、戦前まではそれが普通だったという事実でした。煮しぼりは、食糧難の戦争直後に、増産のために生み出された製法だったのです。
マルツネは、5年をかけて生しぼり製法を現代によみがえらせました。それから30年たちます。
「一時期のはやりものではなく、いつもと同じ味で、主食のように、食卓の真ん中で毎日の食事として愛される、そんな豆腐を目指しています」と近藤専務は目を輝かせて語ります。

原料の大豆の産地を訪ね、栽培状況を確かめたり、生産者と交流したり。親戚同然のお付き合いをしている生産者さんもいます。年に数回、生産者がマルツネの工場見学にも来ています。右の写真は培土作業。除草と土寄せを行います。
一本線は遺伝子組み換えではない印

入荷した大豆は、遺伝子組み換えでないことを必ず社内で検査・確認しています。「国産大豆」に遺伝子組み換え反応が出たことがありました。国内では商業生産されていないはずなのに…。調べると、トラックの中で輸入大豆と交じっていたことが判明。以来、積み荷が交じらないようにしました。
容器にもこだわりアリ!

パックから豆腐を取り出しやすくするため、内側を滑らかにする必要があります。そのために容器をつくる“金型”をピカピカに磨き上げているそうです。パックシールは二重に行い、水漏れせずしかもはがしやすくなっています。