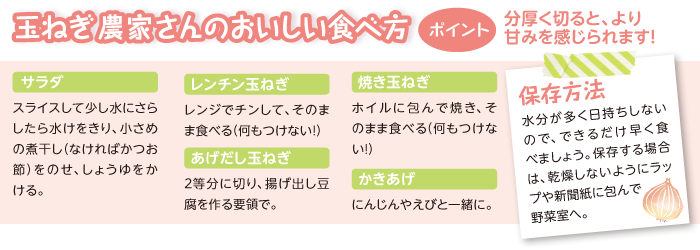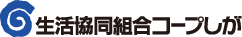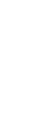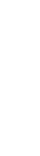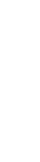やわらかくて甘い春の味覚 島原の新たまねぎ
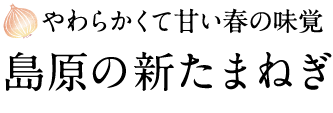

春の味覚、新玉ねぎ。やわらかくて水分が多く、甘みが強いのが特徴です。今回は、長崎県産『島原の新たまねぎ』をご紹介します。産直産地である農事組合法人供給センター長崎を訪ねました。
「島原の新たまねぎ」のココがいいね!
- みずみずしく甘みがある
- 味にこだわり、有機肥料50%以上
- 除草剤不使用の安心野菜
恵まれた長崎の環境

長崎県南島原市は雲仙岳を有する海と山に囲まれた土地。ここで供給センター長崎に加盟する、15名の生産者が新玉ねぎを生産されています。
「この土地は日照時間が長く、年間の平均気温が16度と温暖です。さらに、普賢岳を中心とする雲仙山系がもたらす豊富な水と、よく肥えた土地にも恵まれています。おいしい玉ねぎを作るのにとても適した産地なんです。」と話すのは、供給センター長崎の玉ねぎ部会長・荒木さん。
関西では淡路産の玉ねぎが有名ですが、長崎県も全国シェア5位(兵庫県3位)と、生産量の多い地域です。
生協とのつきあいは約30年、「安全・安心で質の良い農産物を作り、食べてもらうことでお互いを支えあう。人や地球に優しい健康的な食生活をずっと続けていける農業発展」という産地の思いと生協の思いが合致して、地元生協との取り引きが始まりました。今でこそ重視されるようになった「産直」の考え方を、30年前から持たれている生産者です。現在ではコープきんきや全国各地の生協と取引されています。
そもそも、新玉ねぎって?

玉ねぎには皮の色や大きさによって、いくつか種類があります。一年中店頭に並ぶ「玉ねぎ」は、日持ちを良くするため、収穫後に乾燥させて出荷されますが、「新玉ねぎ」は、早い時期に収穫され、乾燥させずにすぐ出荷されます。そのため水分が多く、やわらかく甘いのが特徴。保存がきかないため、生産量の調整や生産計画を立てるのが難しいそうです。「早く出荷できるよう、植える時期を早めにするなどして、計画を立てながらすすめますが、冬の寒さにとても弱いので、育てるのが難しい野菜です」と荒木さん。
おいしさを最優先したこだわりの育て方
この地域で生産される新玉ねぎは、その大部分が段々畑で育てられます。日当たりが良好な反面、土地の形状から農作業の機械化が難しく、生産はほとんどが手作業だそうです。その上、設立当初から除草剤は使わず、除草も手作業。農薬の散布も慣行栽培の約半分におさえ、安全安心な玉ねぎづくりに取り組まれています。

また肥料で味が変わってしまうことから、農業資材の価格が高騰する中、有機肥料を50%以上と高い割合で使用し、おいしさを追求されています。
畑の土は、火山灰と赤土系の粘土質の土です。肥料の持ちが良い反面、水はけが良くないので、畝を高くするなど工夫と努力を惜しみません。これだけの苦労をされていても、生産は天候に左右されるそうです。保存が利かない野菜なので、注文数が安定しないと生産量の調整が難しく、出荷できるのは6~7割程度。最近は少量企画が増え、特に数量が予想しにくいそうです。
苗から収穫へ

本畑への植え替え準備。良質な苗を選び、しっかり根付くように根の土をていねいに落します
6月末から7月は、苗床づくりです。種から苗を作るための畑の整備をはじめます。畑の草を刈り取り、土に堆肥や石灰を混ぜ込んだら、畑の土を盛り上げて畝を作ります。
畝を透明のビニールシートで覆い、夏の太陽の熱で殺菌消毒します。手間はかかりますが、農薬をできる限り使わず生産する工夫です。
9月上旬から苗床に種をまき、11月から成長した苗の中でも良質なものを選び、本畑へ手作業で植え替えます。
収穫は2月から。1つ1つ手作業で収穫し、出荷されます。